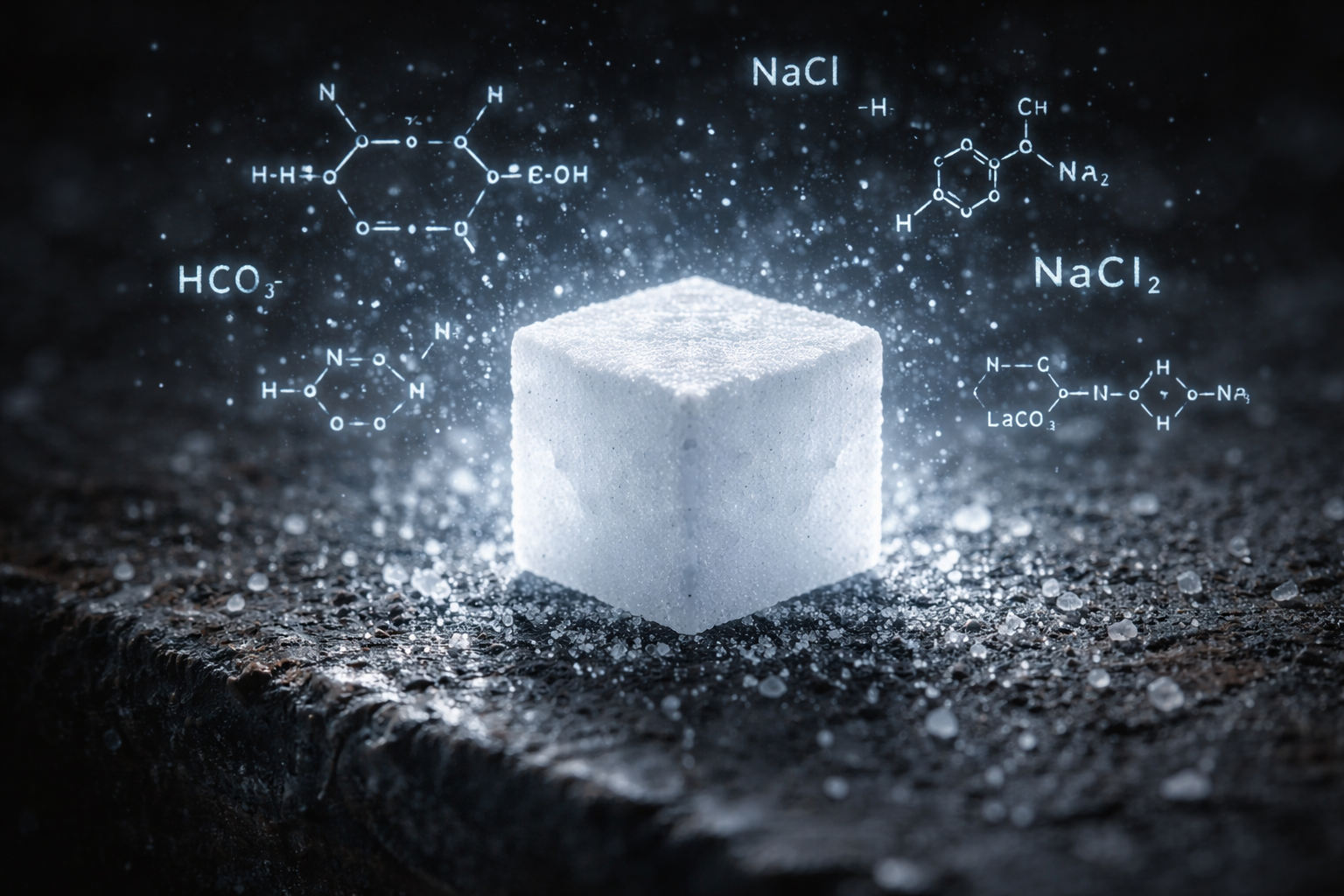バイク整備という「禅」の修行。マザー・ファッカー・プロセスを超えて【『Shop Class as Soulcraft』2/3】

修理工場の「観客」たち
1974年、ロバート・M・パーシグは名著『禅とオートバイ修理技術』の中で、ある修理工場の若者たちをこう描写した。 彼らはラジオをガンガン鳴らしながら、チンパンジーのようにふざけ合い、ピストンの異音を聞こうともせず「タペットだね」と適当な診断を下し、挙句の果てには客のエンジンを台無しにした、と。
マシュー・クロフォードは著書『Shop Class as Soulcraft』(未邦訳)の中で、このエピソードを現代によみがえらせる。彼らの罪は「技術不足」ではない。彼らが自分の仕事に対して「スペクテイター(観客)」だったことだ。 目の前の機械と自分との間に、個人的な関わり(Personal connection)を持とうとせず、ただマニュアル通りに、あるいは惰性で手を動かすこの話を読んで、「なんて無責任な奴らだ」と他人事のように笑ったかもしれない。 だが、笑う前に少しだけ、胸に手を当てて考えてみてほしい。我々が日々、オフィスでPC画面に向かい、右から左へとタスクを「処理」している時の目は、彼らと同じように虚ろではないと言い切れるだろうか? その「心ここにあらず」な態度は、まさに現代の我々が陥っている「現実離れ」した病そのものだ。
「マザー・ファッカー・プロセス」という通過儀礼
休日の昼下がり、愛車の自転車や、あるいは古い家具を修理する時間は、至福のひととき……ではないことが多い。特に、古いモノを相手にする場合、それは「忍耐の限界」を試される苦行となる。
著者はある日、古いホンダ・マグナV45の修理に挑み、固着したクランクケースカバーと格闘する。叩いても、こじっても、潤滑油を差しても、カバーは微動だにしない。まるで物理法則そのものが自分を拒絶しているかのように。 ここで、著者が「マザー・ファッカー・プロセス(Motherfucker process)」と名付けた、ある種の通過儀礼が幕を開ける。
まず、人は獣のように激怒する。あらゆる罵詈雑言(もちろんマザーファッ〇ー)を叫び、喚き散らし、レンチを壁に投げつけたくなる。そして疲れ果て、絶望的な虚脱感の中でタバコを一服する(著者の場合は、近くのストーブでズボンに引火して我に返るというオチがついた)。 だが、この「敗北」こそが重要なのだ。怒りが去った後の静寂の中で、ようやく「自分の思い通りにしよう」という傲慢なナルシシズムが消え去る。自我を捨て、虚心坦懐に機械と向き合ったその時、指先に微妙な感覚が戻り、あれほど固かったカバーが「パカッ」と嘘のように外れるのだ。
「メカニック・ハイ」への到達
機械整備とは、自分の思い通りにならない「他者(物理法則)」と向き合い、自分のエゴをへし折られる修行である。そのプロセスを経た時、我々は「メカニック・ハイ」とも呼ぶべき没頭状態に入る。
錆びついたパーツを磨き、グリスを塗り、正しいトルクで締め付ける。その作業中、我々は「自分」を忘れる。著者はこれを、作家であり哲学者でもあるアイリス・マードックの言葉を借りて「アンセルフィング/unselfing(脱自己化)」の状態と呼ぶ。 自転車のブレーキを調整したり、緩んだ棚のネジを締め直したりしている時、あなたは単に修理をしているのではない。世界と直接プラグインし、情報のノイズから解放された、静寂な時間を過ごしているのだ。それはまさに、パーシグが50年前に説いた「禅」の境地そのものである。
手を汚し、世界と和解するための道具
手を汚し、世界と和解するための道具
今週末は、窓の掃除でもいい、玄関の隅のホコリを吸ったり、シンクのカビや油汚れを取るのでも良い。自分の手を使って、物理的なモノの状態を「快復」させる作業に没頭してみよう。その時、あなたの指先の汚れは、あなたが確かにこの世界に存在し、世界に働きかけた証拠となる。
達成感を感じやすいという意味では、自転車の錆びついたチェーンのメンテナンスがおすすめだ。Before/Afterでの乗り心地の変化がピカイチだからだ。そもそも「自転車ってメンテするの?」と驚く人もいるが、放置されているからこそ、劇的に蘇る。 この儀式を味わうために、私はいくつかの「相棒」を用意する。 まずは、『ニトリル手袋』。素手の感覚を損なわずに怪我から守る、現代の皮膚だ。次に、『スコット(Scott) ショップタオル』。頑丈で油を吸い、繊維を残さない青い紙。 これを使って『ワコーズ チェーンクリーナー』でゴシゴシと汚れを落とし、仕上げに『ワコーズ チェーンルブ』を一吹きする。最後にタイヤに空気を入れれば、驚くほど軽やかに走る自転車が復活する。
クリーナーで汚れを落とす時、心の中の「曖昧なモヤモヤ」も一緒に洗い流されていることに気づくだろう。包丁を研ぐのと同じで、時々面倒を見てやると、道具の真の実力が戻り、使うことがより楽しくなる。 もちろん、明らかに元に戻せる自信がなかったり、破壊工作になりそうなら、プロに任せるのが賢明だ。破壊と修理の違いは、紙一重なのだから。